
マルシェとはフランス語で「市場」を意味し、現地では生活に根付いた買い物の場として親しまれています。一方、日本では特別なイベントとして企画されることが多く、生産者や作り手と消費者が直接やり取りできるのが大きな魅力です。実際に参加してみたいと思っても、仕組みや流れがわからないこともあります。
そこで今回は、マルシェの特徴や出店するにあたって押さえておきたいポイント、準備しておきたいものなどについて解説します。
目次
マルシェとはどういうもの?

マルシェとは、「市場」を指すフランス語です。フランスでは、市民が食材や雑貨などの日常の買い物をする場所として定着しており、土日を含む週3日程度同じ曜日や時間に定期的に開催されます。朝7時前後から午後3時ごろまで続くことが多く、生活に欠かせない存在です。
一方、日本のマルシェはフランスのものに比べると規模が小さく、定期開催よりもイベントとして企画されるケースが中心です。非日常的な体験やお祭りのような雰囲気を楽しむ場として親しまれています。
販売される商品は食材や雑貨が中心で、ファーマーズマーケットや青空市のように、生産者と消費者が直接顔を合わせて売買を行える点が魅力です。
つまり、日本では「特別なイベント」として、フランスでは「日常生活の一部」として位置づけられているのがマルシェの大きな違いといえます。
マルシェの形態

マルシェは、目的に応じてさまざまな形態があります。目的によって開催場所も異なるため、ターゲットとする客層に合ったマルシェへの参加が重要です。
ここでは、マルシェの形態について紹介します。
都市型マルシェ
都市型マルシェは、都市の人通りが多い中心部で開催されるマルシェです。大きなビルのエントランスや駅前広場、地下の通路など、アクセスが良く集客がしやすい場所で開催されます。
商業施設内で開催されるケースもあるので、気軽に足を運んでもらえるのは大きなメリットです。
地域密着型マルシェ
地域密着型マルシェは、比較的小さなコミュニティを対象に開催されるマルシェです。地元の商店街や公園で開催されるのが一般的で、公民館などの公共施設を使う場合もあります。
地元で採れた農産物や加工品、特産品などを販売し、住民同士の交流を目的としています。地域の恒例行事として定着しているところもたくさんあります。
観光市場
観光地にある道の駅や商店街などでは、観光客向けのマルシェが開かれるケースもあります。観光客が手に取りやすい地元の特産品やお土産品、工芸品などが販売されるのが一般的です。常に観光客でにぎわっているため、地域の経済の活性化に貢献しています。
クラフトマーケット
クラフトマーケットは、ハンドメイドの雑貨やアクセサリー、洋服などを販売するマルシェです。クラフト作家が集まって、大小さまざまな規模のマルシェが開催されます。
クラフトマーケット専用のイベント会場で開催されるのが一般的です。また、ギャラリーなどで通年開催されているものもあります。クラフト作家の作品を直接手に取って見たり買ったりできるので人気があります。
骨董市・蚤の市
アンティーク雑貨や古着、古本などを販売するマルシェは骨董市や蚤の市などと呼ばれます。古いものに価値を感じる方や、掘り出し物を見つけるのが好きな方におすすめのマルシェです。
開催場所は公園やイベント会場、神社などが多く、有名なイベント化しているものもあります。
マルシェとほかのマーケットの違い

マルシェと似た言葉に、マーケットやフリーマーケット、商店街などがあります。これらの違いについて下記の表にまとめました。
| 項目 | マルシェ | マーケット | フリーマーケット | 商店街 |
| 主な販売者 | 生産者・個人 | 小売業者 | 個人(不用品) | 個人商店 |
| 主な商品 | 野菜・果物・加工品・雑貨 | 食品・日用品(仕入れ品) | 不用品・古着 | 食料品・日用品・サービス |
| 販売スタイル | 生産者が直接販売 | 店舗が仕入れて販売 | 個人が不用品を販売 | 店舗ごとに営業 |
| 特徴 | 新鮮・一点もの・作り手の想いが伝わる | 安定供給・価格重視 | リユース・節約志向 | 地域密着・常設 |
| イベント性 | 期間限定・イベント的開催 | 常設または定期開催 | 不定期開催 | 常設 |
| 地域との関係 | 地域活性化・交流の場 | 消費活動の場 | 節約・エコ意識 | 地元住民との日常的つながり |
つづいて、マルシェと他のイベントの違いをみていきましょう。
マルシェとマーケットの違い
マルシェとマーケットはどちらも食材や雑貨を扱いますが、下記の点が異なります。
・マルシェ:個人店や生産者が1ヶ所に集まり営業している集合体
・マーケット:生産者から食材を買い上げ販売しているお店
マルシェでは生産者が直接商品を販売できるため、商品にかける思いやこだわりを消費者に伝えられます。
マルシェとフリーマーケットの違い
マルシェとフリーマーケットには、下記のような違いがあります。
・マルシェ:野菜やフルーツなどの新鮮な食材が中心
・フリーマーケット:中古品や古着などの販売が中心
マルシェとフリーマーケットを掛け合わせて「マルシェ」として開催されるケースもあります。
フリーマーケットは、節約志向の消費者から人気が高く、リユースやリサイクル意識の高まりもあって支持を集めています。マルシェは地域コミュニティの活性化を目的として開催されるケースが多く、子どもから年配の方まで幅広い世代が訪れる交流の場となっています。
マルシェと商店街の違い
商店街は、複数の個人商店が集まった常設エリアで、地域に根ざした店が多い点が特徴です。対面販売や手厚いサービスで人情味のある交流が生まれますが、大型スーパーやネットショッピングの普及により、客足が減少している場所も少なくありません。
下記は、マルシェと商店街の主な違いです。
・マルシェ:生産者が直接販売し、中間マージンが発生しない
・スーパー・商店街:生産者から仕入れた商品を販売する
マルシェは中間業者を介さないため価格を抑えやすく、消費者は新鮮で質の高い商品を比較的安価に入手可能です。さらに、生産者と直接会話できるため、商品の背景や生産者の想いを伝えられるのも魅力です。
マルシェ出店のメリット

ここでは、マルシェ出店のメリットを4つ紹介します。
出店費用が抑えられる
マルシェへの出店は、実店舗の開業に比べて初期費用や運営コストを大幅に抑えられる点が魅力です。主な費用は出店料と備品レンタル料で、規模に応じて数千円~3万円程度に収まります。出店料は「固定制」「歩合制」「固定+歩合制」の3種類が一般的です。短期間開催のためランニングコストも低く、飲食店や物販の試験運営にも適しています。
一方で、実店舗は開業に数百万円から1,000万円規模の資金が必要です。人件費や光熱費などの固定費も毎月発生します。
出店にかかる費用は下記のとおりです。
| 実店舗 | マルシェ出店 | |
| イニシャルコスト | 約1,000万円(物件賃貸費・内外装工事費・備品購入費など) | 数千円〜3万円程度(出店登録料・設備レンタル費など) |
| ランニングコスト | 約20万円〜(人件費・光熱費など) | 約1〜5万円(備品レンタル費・電源使用料など) |
| 準備期間 | 数か月〜半年以上 | 短期間で可能 |
| 出店形態 | 常設・長期運営 | イベント単位・短期開催 |
低コストで始められるマルシェは、実店舗をすでに持つ事業者にとっても、認知拡大や新規顧客獲得の場として有効です。
店舗の認知拡大につながる
マルシェは、生産者や個人が多く出店しており、商業施設ではあまり見かけない商品や、ハンドメイドの一点ものなど、珍しいアイテムが並ぶのが魅力です。消費者にとっては新しい発見や掘り出し物を探す楽しみがあり、その特別感から幅広い年齢層の地元住民や観光客が訪れます。
このような場に出店すると、普段はお店に足を運ばない新たな顧客層にアプローチでき、実店舗の存在を知ってもらうきっかけにもなります。出会いを通じて興味を持ってもらえれば、後日お店を訪れてくれる可能性も高まるでしょう。また、来場者に喜んでもらえれば、インターネットやSNSを通じて体験を発信してくれる場合もあり、口コミによる宣伝効果も期待できます。
さらに、規模の大きなマルシェでは1日で5,000〜1万人以上が訪れることもあり、多くの来場者に商品やサービスを知ってもらえるチャンスです。開催地域を変えることで、実店舗のエリア外にも認知を広げられます。効果的に広告効果を発揮し、売り上げアップにもつながります。
消費者と直接コミュニケーションが取れる
マルシェに出店すると、お客様と直接対話できるため、貴重なフィードバックをすぐに得られます。これは、商品やサービスを改善し、質を高めていくうえで非常に役立ちます。
お客様と積極的に関われば、潜在的なニーズを掘り起こせます。これが、次の商品やサービスを開発するための重要なアイデアソースとなるでしょう。
マルシェは個人が直接販売を行う場であるため、消費者とダイレクトに交流できます。自身で商品の魅力を伝えられるため、より具体的で的確な情報を発信でき、消費者の反応や意見もその場で聞き取れます。こうしたやり取りは市場ニーズの把握に直結し、得られた知見を今後の事業展開への活用が可能です。
消費者にとっても、生産者の顔が見える安心感に加え、食材を使った調理のコツやハンドメイド作品の制作秘話などを直接聞ける貴重な機会になります。商品のストーリーや作り手の想いを伝えると、消費者の共感を得やすくなり、信頼関係の構築にもつながります。
出店者同士の人脈が増える
マルシェには、さまざまな出店者やビジネスオーナー、クリエイターが集まります。同業者はもちろん、異業種の事業者とも接点が生まれるため、新たな取引先の獲得やコラボレーションのきっかけにつながります。
新たなビジネスのつながりが得られれば、定期的な情報交換や共同プロジェクトなど、多くのメリットが期待できます。また、競合他社の出店を観察すれば、市場のトレンドや新たなアイデアを把握する機会が得られるでしょう。競合他社がどのような戦略を採用しているかを理解し、自社戦略の調整が必要です。
マルシェ出店のデメリット

マルシェ出店には魅力的なメリットがある一方、注意すべきデメリットもあります。事前に理解し、適切な対策を取りましょう。
売上が天候に左右されやすい
マルシェは屋外で行われる場合が多く、雨や台風などの外的要因を受けると来客が減少し、売り上げが厳しくなるケースがあります。極端に暑い日や寒い日でも客足が伸びず、収益の安定性が低くなりがちです。場合によっては天候により開催自体が中止になることもあります。
そのため、天候が悪い可能性も考慮しつつ、適切な在庫管理や出店計画を立てましょう。具体的には、雨風対策グッズを用意し、痛みやすい野菜や果物、生鮮食品を販売する場合には、品質を保てるような管理体制を整えておく必要があります。
ひとりで出店するのは大変
マルシェ出店では商品やサービスの提供だけでなく、ブースの設営や撤収なども行う必要があります。またディスプレイを事前に考え、使用する道具を準備する必要もあるでしょう。
これらをひとりで行うと膨大な労力や時間がかかります。商品を販売しているときはトイレに行くタイミングも難しいでしょう。マルシェ出店は状況に応じてスタッフを何人か用意する必要があります。
思ったように売上が伸びない場合もある
日本のマルシェでは農産物や加工品が大きな割合を占めており、ハンドメイド雑貨やアート作品など食品以外の商品を販売する場合は需要が限られる可能性があります。食品は日常的に必要とされるため集客力が高い一方で、雑貨やアート作品は購入目的が異なり、売れ行きが予想よりも低くなるケースが少なくありません。
さらに、マルシェごとに来場者数や客層が異なる点も売り上げに大きく影響します。規模の大きなマルシェでは集客力が期待できますが、その分競争も激しく、同じカテゴリーの商品が多いと差別化が難しくなるでしょう。マルシェの売上は、競合ブースの数によって左右されるため、出店する場所選びは慎重に行うべきです。同じような商品が並んでいると、お客様が違いを見つけにくくなり、自店の商品・サービスへの注目度が低下し、売上を下げる可能性があります。
一方で、小規模なマルシェでは競合は少ないものの集客数も限られるため、売り上げが伸び悩む可能性があります。また、平日の昼間に開催される場合は仕事や学校があるため来場者が少なくなる可能性がありますが、週末や祝日に開催される場合は多くの来場者が見込まれ、売上の増加が期待できます。
マルシェの開催場所やターゲット層、開催される曜日や時間帯などを考慮したうえでの出店場所の検討が大切です。
マルシェの出店費用はどれくらい?
マルシェの出店はブース単位で費用が発生します。
基本的に、イベント規模が大きくブースが広くなると費用も高くなり、小規模なイベントであれば安い傾向にあります。
また、地域によっても金額が変動し、都心部などであれば2〜3万円程度かかる場合もあるようです。
自治体が主催するマルシェは比較的安く、1ブース3,000円ほどのケースもあります。
イベントによっては、ブース単位の計算ではなく、売上に対する歩合制を採用する場合もあるため、費用に関しては事前にしっかりと確認しておいた方が良いでしょう。
マルシェ出店で押さえておきたいポイント

マルシェは多くの人が訪れるため、出店すれば商品の魅力を伝える良い機会になります。ここでは、マルシェ出店で押さえておきたいポイントを紹介します。
開催内容で選ぶ
マルシェ出店を検討する際は、まずその開催内容やコンセプトの把握が不可欠です。日本のマルシェはイベント的なものが多く、出店条件が設定されている場合があります。
特定の地域の食品のみを集めたマルシェや、オーガニックにこだわったマルシェなどの場合、その条件に当てはまる商品を用意しなければ出店できません。
また、出店料の支払いで参加可能なマルシェと、面接や審査を経て出店が決まるマルシェがあります。事前に出店条件や審査の有無などを調べたうえで、出店を申請しましょう。
販売スペースの大きさで選ぶ
出店前に、ブースの大きさを必ず確認しておきましょう。取り扱う商品に対して販売スペースが狭すぎると、販売スタッフが作業しづらくなるでしょう。
一方で、販売スペースが広すぎると、お客様が少なく人気がないお店に見えてしまう可能性があります。前もって販売スペースが適切な広さかどうかを確認しておきましょう。
アクセス方法で選ぶ
マルシェに出店するときには、アクセス方法のチェックも欠かせません。駅から遠い、近隣に駐車場がないなどアクセスが良くない場所だと、客足が遠のいてしまいます。出店者用の駐車スペースが確保できず、商品の搬入で困る場合もあるでしょう。
また、アクセスが良い場所でも、路線によって客層が異なる点に注意が必要です。取扱商品のターゲット層が少ない路線に出店してしまうと、思うように集客できない可能性があります。
マルシェ出店までの流れ
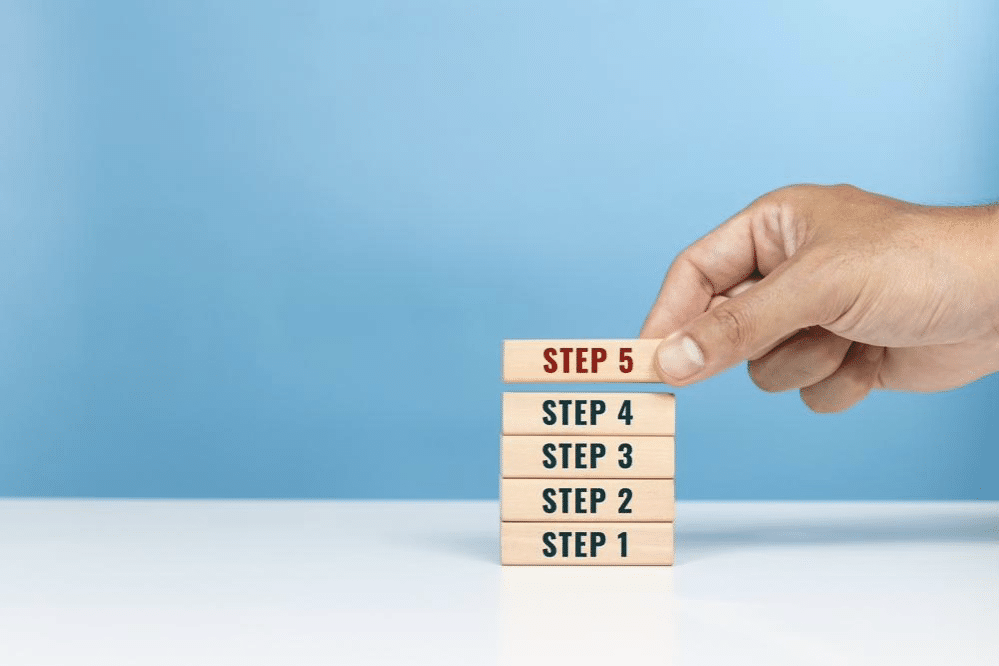
マルシェへの出店を成功させるには事前準備が大切です。当日までにやるべき準備を整理しておきましょう。
イベントに申し込む
マルシェに出店する際、基本的には事前の申し込みが必要です。
開催情報をチェックして、出店条件に合うイベントを探しましょう。一般的にはネットで申し込みができます。
申し込みをしたあと、出店についての案内がありますので、ブース費用や審査の有無なども確認しておいてください。基本的に費用は事前に支払う必要がありますので、期日までに出店料を振り込めば申し込みが完了します。
決済方法を決める
決済を現金のみで対応するのか、クレジットカードや電子マネーなどのキャッシュレス決済にするのか、あらかじめ決めておきましょう。
現金の場合は、お釣りを十分に用意する必要があります。幅広い層に利用してもらえるメリットがある一方で、現金は管理に手間がかかる点や、盗難リスクがある点に注意が必要です。
盗難防止や会計時間の短縮のために、キャッシュレス決済を取り入れるのもおすすめです。近年は、マルシェなど1日~数日単位で利用できる、キャッシュレス決済代行サービスも登場しています。
ただし中には導入まで1か月程度かかるものや、事前の審査が厳しいサービスもあります。出店を決めたら早めに決済代行サービスの選定が大切です。
必要なものを用意する
販売する商品はもちろんですが、消費者に魅力が伝わるようなPOPやブースの個性が出る備品の準備なども大切です。
ほかにも、各商品の値札や陳列するための什器、商品を入れる袋や包装用の新聞紙、ゴミ袋など、出店から販売を想定して必要となる備品の準備をしましょう。
レンタルができない場合には、必要に応じてテーブルや椅子、コンテナ類なども用意しなければなりません。
また、マルシェ終了後にもリピーターとなってもらえるように、ショップカードやSNSアカウントにアクセスできるQRコードも印刷して準備しておくとよいでしょう。
SNSやブログで宣伝する
マルシェへ出店する際は、集客力を上げるためにも早めの告知が重要です。SNSやブログを運営している場合、できる限り早く出店情報を宣伝すれば、より多くの方に情報が拡散できる可能性があります。
特にSNSでは、マルシェの名前をハッシュタグにつけるなど、フォロワー以外にも宣伝内容を見てもらえるよう工夫しましょう。
当日販売する商品が決まっているのであれば、その情報や大まかな金額についても記載しておくと親切です。
実店舗を運営している場合は、上記に加えてチラシやはがきなどでのお知らせも有効です。
マルシェ出店の流れ
マルシェ出店の当日の流れについて、5つのステップに分けて解説します。当日の流れや注意点は、下記のとおりです。
マルシェに搬入する
イベントによって、搬入日や時間が決まっています。マルシェは、当日の1時間程度前から搬入できるケースがほとんどです。
事前に通知された搬入時間内に受付を済ませて、開始時刻までに準備を終える必要があります。荷物の搬入口や出展者用の駐車場エリアも指定されている場合があるため、注意事項や当日のルールは事前に隅々まで確認しておきましょう。
ブースを設営する
開始時刻から商品を販売できるように、時間に余裕をもって設営します。
風が強い日や小雨が降っているときなど、当日の天候に左右されないディスプレイを心がけましょう。例えば、プライスカードが飛ばないようにピンやテープで留めるなどの工夫が必要です。
また、次回以降の参考となるように、設営完了後の写真を何枚か撮っておきましょう。
マルシェで販売
開始後はお客さんの動きを見て、ディスプレイを適宜修正します。見えにくい部分を改善するほか、立ち寄りやすい雰囲気の演出も大切です。
トイレなどで離れるときは、お金や商品の管理に注意しましょう。一人参加の場合は、席を外していると分かるようなボードも必要です。
ブースを撤収する
閉場時間になったら速やかにブースの撤収作業を行います。借りていた備品は指定場所に返却して、ブース内にゴミや忘れ物が残らないように注意します。
マルシェから搬出する
イベントごとに搬出時間も決まっています。搬出時間内に会場や駐車場から出られるように、準備を済ませておきましょう。
帰宅後はSNSなどで無事にマルシェ出店が終わったことや、次回の参加予定を告知しておきます。当日は開始前と終了後に周囲のブースへ挨拶をすると、出店者同士のつながりもできて情報収集につながります。
マルシェ出店で成功するためのコツ
日本のマルシェは、期間限定のイベントとして楽しむスタイルが一般的です。マルシェ出店を成功させるなら、来店されたお客様が「楽しかった」と思えるような雰囲気作りを心がけましょう。
ディスプレイや接客の工夫は、出店者の売上アップや認知拡大につながります。さらに、マルシェは地域活性化や観光誘致にもつながり、地域住民や観光客との交流を生む場となります。
ここでは、マルシェ出店で成功するためのコツをご紹介します。
計画的に準備する
マルシェ出店を成功させるには、明確な目標の下で計画的な準備が欠かせません。まずは開催テーマやターゲット顧客を調査し、自社商品との相性や需要を分析しましょう。出店料や交通費、備品購入費などの経費を計算し、現実的な売上目標の設定が大切です。
さらに来場見込み数や競合状況、当日の天候も加味し、より具体的で実行可能な数値目標を設定しましょう。
緊急時に備える
マルシェ出店の成功には、雨天やトラブル発生といった緊急時への備えが欠かせません。事前に想定されるリスクを洗い出し、対策を講じると、万が一の事態にも落ち着いて対応できます。
例えば、雨や風に備えてテントやカバーを準備し、什器を固定できるグッズも用意しておくと安心です。季節ごとの気温に応じて熱中症や防寒対策をして自身やスタッフの体調管理にも注意しましょう。
SNSを活用する
SNSは必須ではありませんが、活用すれば集客やPR効果を高められます。事前にはイベント告知や店舗情報を発信し、当日は写真や動画を投稿し来場者と共有しましょう。
さらに、ショップカードにSNSやホームページのURLを記載しておけば、来場後も顧客との関係性を維持できます。イベント終了後には会場の様子を発信すればリピーター獲得や次回開催に向けたPRにもつながります。
魅力的なブースを作る
マルシェへ初めて出店する際には、ほかのブースに埋もれないよう、来場者を惹きつける魅力的な空間づくりが大切です。
特に陳列ディスプレイはブースの顔となるため、商品がひと目で理解できるようシンプルかつ分かりやすい配置を意識しましょう。
さらに、商品だけでなく「入りやすい」と感じてもらえるような明るく丁寧な接客も来場者の印象を左右します。人気ブースに人が集中すると混雑や不快感を招くため、配置や案内表示を工夫して回遊しやすいレイアウトに整える工夫も必要です。
マルシェ出店を検討するならコンテナ型店舗がおすすめ
マルシェ出店は個人ビジネスの発展だけでなく、地域活性化にもつながります。地元住民や観光客との交流は、商品の販売にとどまらず、新しい出会いや人とのつながりを生み出します。日常では出会えない顧客層にアプローチできるのも魅力です。
出店を検討している方は、初期費用を抑えつつ実践的にチャレンジできるマルシェの活用がおすすめです。まずは気軽に一歩を踏み出して、自身のサービスや商品の可能性を広げてみてください。
マルシェの出店を考えているなら、ぜひ「HIRAKELレンタル」のHIRAKEL マルシェをご利用ください。
HIRAKELマルシェには日額レンタルコース(税込19,800円)と月額レンタルコース(税込138,600円)があります。
レンタルアイテムは、マルシェブース、ガーランド、スタンドボード、フックボード、クリップライトと、イベントに必要な物品が一式そろっております。デザインがおしゃれで、コンセプトに合わせて装飾もできるため、ほかのお店との差別化が図れます。詳しくは下記のサイトをご参照ください。
無料相談、無料見積りも受け付けていますので、メールやお電話にてお気軽にお問い合わせください。
HIRAKELレンタルはこちら

まとめ
マルシェは個人規模のお店が集まり、食材や雑貨を販売する期間限定のイベントとして日本各地で人気を集めています。
常設の店舗よりも出店しやすく、生産者が直接お客様とつながれる点も魅力です。ただし、出店条件や審査を受ける場合もあるため、事前に出店希望のマルシェの条件や、審査の有無などについて調べておきましょう。
初期費用を抑えて安心して挑戦したい方には、必要な備品がそろった「HIRAKELマルシェ」のレンタルサービスがおすすめです。おしゃれなデザインで他店との差別化も図れ、初めての出店でも安心してスタートできます。


