
キッチンカーはテナントを借りる必要がないうえ、どこにでも移動できるため、遠方やイベントで出店しやすく、手軽に開業できます。
しかし、キッチンカーを開業する際は「食品衛生責任者資格」「保健所の営業許可」「運転免許」といった3つの資格が必要です。
今回は、キッチンカーの開業に必要な資格や取得方法、それぞれの注意点について詳しく解説します。キッチンカーで開業を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
目次
キッチンカーの開業に必要な3つの資格

キッチンカーでの開業にあたって、必要な資格には以下の3つがあります。
- 食品衛生責任者資格(食べ物を扱うため必須)
- 飲食店営業許可(保健所での許可が必要)
- 運転免許証(キッチンカー運転のため)
なお、調理師免許に関しては必ずしも取得しなければならない資格ではありません。上記の3つの資格を取得すれば開業できるので、キッチンカーは気軽にチャレンジしやすい仕事でもあります。

キッチンカー開業に必要な資格その1.食品衛生責任者
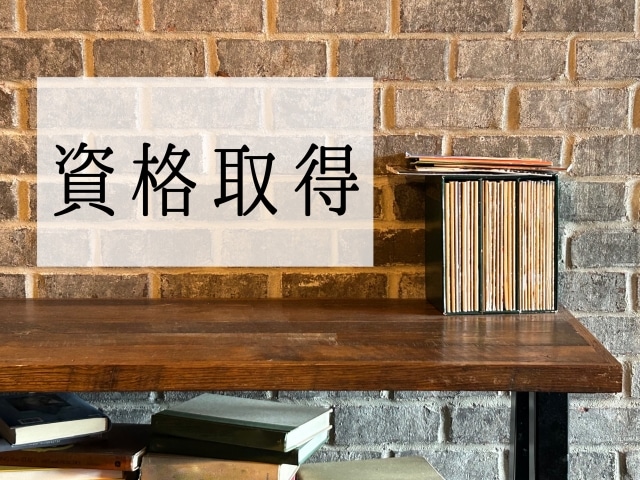
キッチンカーを開業するときは、提供するメニューに関係なく「食品衛生責任者」の資格を取得しておく必要があります。食品衛生責任者とは、全国共通の資格で食品衛生法によって定められた資格です。令和3年6月1日から営業許可施設ごとに資格取得者を置くことが義務付けられました。
以前は「飲食店営業」や「菓子製造業」などメニューに応じた資格が必要でしたが、現在は制度改正により一本化されています。そのため、キッチンカーも1台につき1名の食品衛生責任者を置かなければなりません。
一度取得すれば全国で通用する資格のため、例えば遠方のグルメイベントに出張参加する場合も改めて現地で取得する必要はありません。
取得する方法
各都道府県の食品衛生協会が開催している「食品衛生責任者養成講習会」を受講すると、当日中に受講修了証が発行されます。
講習会は1日(計6時間)のみで終了し、具体的な内容は以下のとおりです。
- 食品衛生学…2.5時間
- 食品衛生法…3時間
- 公衆衛生学…0.5時間
なお、大学で特定の学部の課程を修めて卒業した方や、栄養士や調理師などの免許を取得している場合は、受講が免除されます。
スケジュールは各都道府県によってさまざまなので、受講予定の場合はスケジュールを確認するようにしましょう。資格取得には、講習申込書・本人確認書類(運転免許証・保険証など)・免除対象証明書(免除者のみ)を必要書類として準備する必要があります。
更新期間
食品衛生責任者の資格には、有効期限がないため更新は不要です。しかし、資格取得者には常に新しい食品衛生に関する知識を吸収することが求められています。
数年に一度、実務講習会の受講も義務化されているため、定期的に新しい知識や実務講習会の情報を確認するようにしましょう。
受講にかかる費用
各都道府県の食品衛生協会が開催する食品衛生責任者養成講習会は、およそ1万円〜2万円の費用が必要です。ただし、講習会費用は地域によって異なります。例えば、東京と大阪では以下のとおりです。
- 東京…12,000円
- 大阪…10,500円
なお、地域によっては、講習会の日程別に参加人数の上限が定められており、希望の日程で実務講習を受けられない可能性もあります。早めの申し込みをおすすめします。
資格は全国共通
キッチンカーであれば、他府県で開催されているグルメイベントや遠方での出店など、場所を変えて販売が可能です。
食品衛生責任者の資格は、一度取得すれば全国どこでも適用されます。そのため、イベント出店などで他府県に出向いた際でも、改めて出店する地域で取得する必要はありません。
基本的には、養成講習会修了証書を提示すれば出店は可能です。ただし、手続きは各都道府県の食品衛生協会に確認しておきましょう。
キッチンカー開業に必要な資格その2.保健所の飲食店営業許可
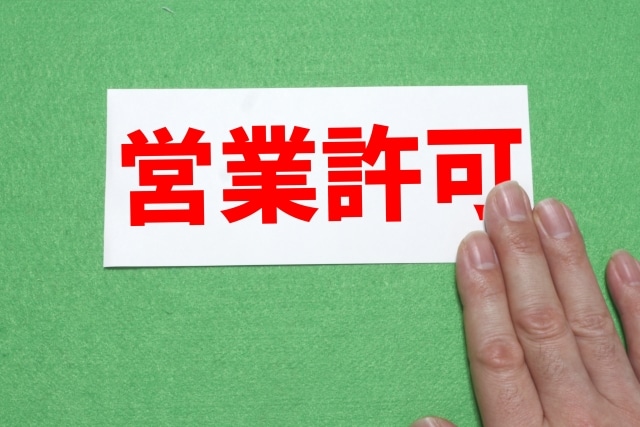
キッチンカーで営業するには、販売地域の保健所から営業許可を得る必要があります。この許可は、車両の設備が食品衛生法に適合していることを証明するものです。
2021年6月1日の法改正でHACCPに沿った衛生管理が義務化され、審査基準は全国的に厳しくなりました。取り扱う食品や販売方法で必要な許可項目が異なるため、事前に管轄の保健所に確認しましょう。
取得する方法
保健所に申請してから営業を開始するまでの大まかな流れは、以下のとおりです。
- 保健所に事前相談する
- 基準を満たしたキッチンカーを用意する
- 申請書類を提出する
- キッチンカーの検査日程を調整する
- キッチンカーの検査を受ける
- 合格後2〜3週間ほどで許可証が発行される
- 許可証を提示して営業スタート
不明点は保健所の担当者に聞きながら進められます。なお、合格後2〜3週間程度で許可証が発行されると記載していますが、地域によって異なる可能性があります。申請を出す保健所に確認して、早めに手続きするのが望ましいです。
事前に相談する
保健所へ急に申請を出すのではなく、事前の相談が必要です。保健所ごとにこまかな条件や見解が異なるため、担当者からアドバイスをもらいながら準備を進めましょう。
また、相談のタイミングはキッチンカーを購入、整備する前が望ましいです。保健所の基準を知らないままキッチンカーを整備すると、許可が下りなくなるうえ、基準を満たすために再度整備を行わなくてはなりません。
再度整備の必要性が発生すれば、費用が二重にかかるうえ、オープン予定日が大幅にずれ込むデメリットもあります。
基準を満たしたキッチンカーを用意する
保健所で必要な基準を詳しく聞き取ったうえで、キッチンカーの準備に取りかかりましょう。キッチンカーは、専門店での購入がおすすめです。中古のキッチンカーでは、保健所の基準を満たしていない可能性があり、改修が必要になる場合も少なくありません。
キッチンカーの専門店を訪れたら、保健所で得た情報をスタッフに伝え、基準を満たす車両があるか相談しましょう。専門店のスタッフは、営業許可取得に必要な設備の知識が豊富なので、あなたの事業に合った適切なキッチンカー選びをサポートしてくれます。
必要書類を提出する
保健所の営業許可を取得するのに必要な書類は、各地域によって異なります。必ず事前に、管轄の保健所に問い合わせて確認しておきましょう。
参考までに大阪府茨木保健所での必要書類を以下に記載します。
- 営業許可申請書・営業届出書1部
- 施設図面2部
- 食品衛生責任者の資格を証明する書類
- 自動車営業設備の概要2部
- 露店・自動車による営業に係る確認票2部
- 加工施設の許可証のコピー2部(車内での仕込みが必要な場合)
- 車検証のコピー2部
- 法人の場合は、登記事項証明書
大阪府茨木保健所では上記の書類が必要です。なお、2021年6月1日の法改正により、大阪府内の任意の自治体で許可を取得すれば、大阪府内全域でキッチンカーの営業ができます。
キッチンカーの検査を受ける
申請を出したら、後日保健所の担当者によるキッチンカーの検査が行われます。衛生面など保健所の基準を満たしているかを確認されたあと、問題ないと判断されれば営業許可を取得できます。
キッチンカーの検査が行われるときは、営業者の立ち合いが必要です。キッチンカーがバンタイプか軽トラックタイプかで基準が異なる部分もあるため、事前相談の段階で担当者にこまかく確認しておきましょう。
なお、営業許可は検査に合格後2〜3週間ほどで発行されます。ただし、発行までの期間は地域差があるため、事前に確認が必要です。
更新期間
保健所から取得する営業許可の有効期限は、どの地域でも概ね5年と定められています。
更新時は、設備が経年劣化で保健所の基準を満たさなくなっている可能性も考えられます。ある程度の改修費も視野に入れておきましょう。
なお、期限までに更新をしなければなりません。有効期限は飲食店営業許可証に書かれているので事前に確認しましょう。更新日の1ヶ月前など、地方自治体によっていつまでに更新が必要かは異なるため、自治体からの案内を確認したうえで指示に従いましょう。
取得にかかる費用
地域によって取得にかかる申請手数料には多少の違いがあります。例えば、大阪府茨木保健所に飲食店営業許可を新規で取得する場合だと、16,000円必要です。更新には、12,800円がかかるため、必ず用意しましょう。

チェックされる条件
保健所の営業許可を取得する際に、主にチェックされる条件がいくつかあります。事前にチェック項目を知っておき、申請前には十分に確認してから審査に臨みましょう。
- 厨房区画の明確化(厨房とそれ以外の区画を明確に仕切る)
- シンクの数と大きさ(2槽以上設置、幅45cm×奥行36cm×深さ18cm以上)
- 給水・排水タンクの容量(調理や清掃に必要な水を十分に供給する)
- 床面・内壁の構造や材質(排水がよい清掃しやすい構造)
- 収納ケースや棚の設置(扉付きの食器棚設置するなど)
- 石けんや消毒の設備(こまめな衛生管理が非常に重要)
- 換気設備(調理中に発生する臭いや煙を排出できる装置が必要)
- ゴミ箱の設置(ゴミの分別が適切に行われるか)
- 冷蔵庫・冷凍庫の設置(温度計の設置必須)
- 蛇口の形状(感染予防できる装置を選ぶ)
自治体によっては上記以外の条件もある場合が考えられます。内容を確認した上でキッチンカーを選びましょう。
出店する都道府県ごとに許可が必要
保健所の営業許可は、出店する都道府県ごとに申請が必要です。保健所が定める基準は地域ごとに異なっており、例えば大阪のキッチンカーが東京へ出張する場合は、改めて東京で営業許可の取得が求められます。また、複数のキッチンカーで営業する事業者は、車両ごとに取得します。
出店を予定している地域がある場合は、早めにその地域の保健所へ連絡をして相談しておきましょう。
仕込み場所の確認も必須
仕込みが必要なものを販売する場合は、保健所で許可を得た仕込み場所を確保しなければなりません。
各保健所で仕込みに対する見解も異なります。そのため、仕込みに該当する工程と該当しない工程に差があります。
保健所へ相談する際は、仕込みに関してもあらかじめ確認しておくと安心です。キッチンカーの仕込み場所についての詳しい情報は、以下の記事をご参考ください。

キッチンカー開業に必要な資格その3.運転免許証

キッチンカーは調理スペースやプロパンガスなどの設備がある分、特別な運転免許証が必要なのでは、と不安になっている方も多いでしょう。キッチンカーを開業するうえで知っておきたい運転免許証のルールは、大きく分けて2つあります。
普通免許でもキッチンカーは開業できる
キッチンカーを運転するうえで、特別な免許や資格は必要なく、普通免許を取得していれば運転可能です。ただし2007年以降に免許を取得した方は、運転できる車両の条件が変更されている点に注意してください。運転免許の取得時期で、以下のとおり運転できる車両の条件が異なっています。
- 2007年6月1日までに取得している場合:8トン未満
- 2007年6月2日~2017年3月11日までに取得している場合:5トン未満
- 2017年3月12日以降に取得している場合:3.5トン未満
キッチンカーは車両総重量が5トン未満で、最大積載量2トン以上3トン未満の車両が使用されています。2017年3月11日までに免許取得している方は普通免許のみで問題なく運転できますが、2017年3月12日以降に免許取得した方は準中型免許も必要です。
牽引タイプの場合は車両総重量と全長に注意!
エンジンが非搭載の、いわゆる牽引タイプのキッチンカーの場合も、車両総重量によっては普通免許のみで移動できます。牽引する車両が750kg以下の場合は、牽引免許を改めて取得する必要はありません。
車両総重量が750kgを超えると牽引免許が必要となるため、キッチンカー用の車両を手配するときは注意しましょう。
また、トレーラー+牽引車の全長が12m未満(高さ3.8m未満・全幅2.5m未満)である必要もあります。

開業に必要な資格と許可が揃ったら「出店場所」を確保しよう!

食品衛生責任者や免許証、保健所の営業許可を取得したら、次は出店場所の確保です。出店場所は、キッチンカーの売上を左右する、重要なポイントといえます。
また、初期費用を抑えつつ飲食店を開業したい方は、コンテナ型店舗もおすすめです。 低リスクで購入、レンタルもできるのでこれまで飲食店や屋台を経営したことがない方でも安心です。
HIRAKELは、様々なプランから自分にあったものを選ぶことができ、他社のキッチンカーよりもローコストで屋台開業ができるサービスです。
まとめ

実店舗を構えるよりも手軽に開業できるキッチンカーですが、飲食物を取り扱う以上、実店舗と同様に資格や営業許可が必要です。営業許可を取得する際には、キッチンカーの設備も確認されるため、事前に管轄の保健所で相談し、万全の準備をすると安心です。
HIRAKELでは、他社のキッチンカーよりもローコストで飲食店の開業を目指せます。初期費用を抑えつつ開業したい方は、HIRAKELへお気軽にご相談ください。


